 東京大学が秋入学制の導入を検討しているという話が少し前にあった。何でも、優秀な外国人の入学を促す狙いがあると言う。他の大学も巻き込んで、秋入学を推進しようとしているらしい。そのニュースを聞いた時は、こう思ったものだ。「桜が咲かない入学シーズンなどありえない、日本の文化を何だと思ってるんだ、トーダイ、けしからん。」
東京大学が秋入学制の導入を検討しているという話が少し前にあった。何でも、優秀な外国人の入学を促す狙いがあると言う。他の大学も巻き込んで、秋入学を推進しようとしているらしい。そのニュースを聞いた時は、こう思ったものだ。「桜が咲かない入学シーズンなどありえない、日本の文化を何だと思ってるんだ、トーダイ、けしからん。」
私の遠い昔の学生時代の記憶でも、卒業、入学というのは特別な時期として思い出される。そして、そこには必ず桜が咲いていて、心改まる、そしてどこか切ない、ムズムズするような、薄いピンク色の、陽射しの眩しい、明るい世界の出来事として、蘇ってくる。桜を歌った歌もまた、卒業、入学、人生の門出をサクラのイメージで歌った名曲が多い。福山雅治の桜坂、コブクロの桜、嵐のサクラ咲ケなどなど。
しかしながら、しばらく経ってみると、少し考えが変わってきた。東大に優秀な外国人学生が入学するかどうかはこの際どうでもよいが、必ずしも入学式に桜が咲いてなくてもよいのではないかという気持ちになってきた。桜は、歴史的文化的に、日本人にとって特別な花であることは間違いないが、進級、進学と結びつける必然性はないと思い直した。それは単に勝手な思い込みだと言われれば、反論できない。
それで、入学に限らず、社会全体で秋に年度が変わることのメリットを、贔屓目なく考えてみた。すると、意外に秋が新年度だと、良い面もあるように思えてきたのだ。それは、季節が人間の気分に与える作用から、秋に年度が切り替わった方がよいのではないかと思えてきたと言うことである。
それは、こういう事である。寒い冬が開け春になると、気分はハイになる。新しことに挑戦したくなり、エネルギーを新たなことに向けたくなる。このシーズンは、自分がこれから進むべき道を考えるのにピッタリの時期なのである。ところが、現状では、春に新しい年度が始まる。つまり、新しい進路に進んだ直後に、進むべき道を考えることになり、これでは、会社に入った途端に別の道に進みたくなるようなものではないだろうかと思われてきたのである。
これに対して、秋入学であれば、年度の中頃にやってくる春の時期に、そのハイなエネルギーを使って自分の進むべき未来を夢見る時期とし、秋までの間に、その考えを深めることができる。そして涼しくなってきた頃、実際に新たな進路に進む時期がやってくる。これは、春の燃え立つエネルギーと、実際の進路選択までの熟慮期間と言う意味で、合理的なタイミングだと思うのである。この合理性の前には、入学式に桜が咲いているかどうかは、どっちでもよかろう。
と、思うと、秋入学も悪くはないのではないか。実際、企業の人事異動は、4月と10月の2回の会社とか、秋に年1回のみと言う会社も結構あるようである。夏休みも、1年を終えた後なら、もっと有意義に過ごせるようになるのではないか、とも思う。秋入学、外国との関係だけでなくても、意外といいところもあるように思う。
2012.9.28(金)

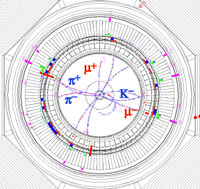

コメント