
「月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり。」松尾芭蕉の「奥の細道」の有名な書き出しである。子供の頃からなぜか好きな文章で、声に出して読んでも調子がよく、今でも時々口ずさむことがある。でも、その意味は、考えてみると奥深くて、よくわからない。行きかう年、つまり年月が旅人だと言っている。一体どういう意味なのだろうか?
「時間」が「旅人」だという意味を素直に解釈してみると、時間というものは、やってきて、そして過ぎ去ってゆく、目の前を通り過ぎてゆくものだという意味で、旅人に似ているという意味だと思う。「時間」という目に見えないものを、目に見える「旅人」に例えたところに斬新さがあるようにも思われる。まぁ、これは余談だが、アインシュタインの相対性理論でも、3次元空間と時間は切っても切れない関係にあって、4次元時空として扱わないと、この世の中の現象は記述できないと言っている。
ただ、芭蕉の「月日は百代の過客」は、芭蕉オリジナルではなく、李白の漢詩、「春夜宴桃李園序」を出典としている。李白の詩には、「夫れ天地は万物の逆旅(げきりょ)にして、光陰は百代の過各なり。」とある。逆旅は旅館、宿屋の意味で、「この世界は全ての物が泊まる宿屋のようなもので、月日は永遠の旅人のようなものである」という意味で、芭蕉はこの表現を借りている。昔の文化人は、李白の漢詩は共通の教養としてあったと思われるので、奥の細道の冒頭を読んでも「あぁ、李白のね」とすぐに分かって、その意味も、李白の詩の世界を思い描きつつ味わったことであろう。その辺は古典の教養がある人をうらやましく思う。
李白は、桃李園という宴会場で宴会を催すに際して、一言申し上げるあいさつの詩を書いたということで、光陰は百代の過客と言った後、こう続く。「しかして浮生は夢の若し、歓を為すこと幾何(いくばく)ぞ。」日本語では、「時間の流れに比べて、人生は夢のように儚いもので、楽しいことも長くは続かない。」となる。今から、おいしいものを食べ、おいしくお酒を飲もうというときに作った詩だというのだから、その流れでは、「人生は短いんだから、今この時ぐらい、目一杯楽しもうよ」と言っているのだ。
対して、芭蕉の「月日は百代の過客」の文の後には、「船の上に生涯を浮かべ、馬の口とらえて老いを迎ふる者は、日々旅にして旅を栖とす。古人も多く旅に死せるあり。予もいづれの年よりか、片雲の風に誘はれて、」云々と続く。船頭や馬方(今で言うと運転士的な人)などの職業の人々は、毎日が旅のようなもので、旅の中に住んでいるようなものだ。昔の文人も旅で死んだ人はたくさんいる。自分も旅をしたくてたまらない。と続いてゆき、芭蕉自身の旅に出たいという思いが綴られてゆく。李白が、今を楽しもうと言ったのとは全く違う文脈で「百代の過客」を使っている。
ちなみに、芭蕉が「古人」と言った中には、当の李白も含まれている。李白も相当な旅好きで、中国各地を放浪した挙句、旅先で客死した人で、芭蕉もその生涯にあこがれていたのだと思う。芭蕉自身も、日本中を旅して、数多くの俳句と紀行文を残し、最後は李白と同様、旅の途中で客死した。本望だっただろうと思う。
2023.2.19.日
写真:船頭(無料イラスト)


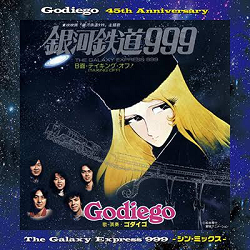
コメント