
英語では、Janurary,Feburaryと各月に個別の名前が付いているのに、日本語は、1月、2月と機械的で、味気ない気がしていた。しかし、そう言えば、日常的には使わないものの、日本語にも、月を表す名前があると思い出した。高校時代に古文で習って以来、久しく使ったことはなかったが、確か、睦月、如月、弥生、と言ったような。日本語、やっぱりなかなか良い、と思って順番に思い出してみた。
ところが、6月だけどうしても思い出せなかった。調べてみたら6月は「水無月」。でも、梅雨の季節に水が無い月とはどういうことだろう?しとしと降り続く雨で水だらけなのに。更に調べてみると、「無」は、「ない」という意味ではなく、「の」という意味だと言うことだ。納得。確かに6月は、水の月。10月の「神無月」は、日本中の神様が出雲に集合するので、神様がいなくなる月だと聞いたことがあったが、この「無」も、「神の月」と言われた方がしっくりする。収穫を神に感謝する、神の月。
睦月、如月、弥生、卯月、皐月、水無月、文月、葉月、長月、神無月、霜月、師走。6月と10月だけ3文字、3月と12月だけ「月」の文字が付かない。このあたりの緩やかな規則性も、「月」らしくて良い。満月はきっちり15日と決まっているわけではなく、ひと月も、30日と決まっているわけではない。如月は、28日だったりする。ひと月の日数がきっちりと決まらないのは、月にまつわる暦が、太陽と地球と月の3体問題を元にしている点に起因する。自然は単純ではないが、よく調べると美しい複雑さが観えてくる。生命が、単純さとカオスの間の領域で生まれることは、複雑系の科学ではよく知られたことだが、月の暦にも複雑さの片鱗を感じてしまうのは、あながち的外れは話ではなかろう。
月の呼び名が言語によって違っていることが気になって、他の言語ではどうだろうかと調べてみた。フランス語、ドイツ語などは英語と似たような感じなのに対して、中国語やハングルは、日本語的に、1月、2月型だった。日本語から見ると、英語もドイツ語も似たようなものなので、西洋で月を呼ぶのに似たようなコトバを使うのはなんとなくわかるが、日本語を含むアジアの言葉が、いずれも1月、2月型なことがちょっと意外だった。特に中国語は、睦月、如月型だと予想していたが、外れた。多分、中国も、日本と同様に昔はもっと優雅な月の呼び名があったのだろうと推測する。
睦月、如月、いい呼び名だと思うし、今後は積極的に使おうかとも思う。でも、1月、2月もまた悪くはない。なぜってそれは、「月」が付いているから。英語は、Janurary,Feburaryと言っても、”Moon”を思わせる言葉ではない。対して、日本語は、機械的であるにせよ、「月」を単位に使っている。この点が、私には高ポイントである。科学的でもあるし、同時に満ち欠けするあの丸い形を連想させて情緒的にも感じる、よい呼び名であるように思うのだ。ジャイアントインパクトとプロゲステロンの話に付き合っていただいた人なら、この感じを共有してもらえると思う。
2017.4.2(日)
写真:月、Wikipediaより
写真:月、Wikipediaより


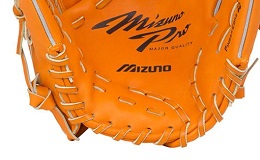
コメント