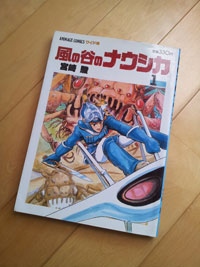 前回、理科年表が自分にとっての古典の1つだと書いた。ただ、理科年表を古典と言うにやっかいなことが1つある。それは、理科年表は、毎年更新版が出版されることだ。毎年内容が更新される古典など、聞いたことがない。古典は、本棚の中でも、読み古されて、擦り切れてボロボロになっている本のイメージがしっくり来る。毎年新たに購入する古典というのは、他に例える術もなく矛盾して聞こえる。しかしながら、前回の小文をよんでいただければ、私の感覚も何となく分かってもらえるのではないかと思う。
前回、理科年表が自分にとっての古典の1つだと書いた。ただ、理科年表を古典と言うにやっかいなことが1つある。それは、理科年表は、毎年更新版が出版されることだ。毎年内容が更新される古典など、聞いたことがない。古典は、本棚の中でも、読み古されて、擦り切れてボロボロになっている本のイメージがしっくり来る。毎年新たに購入する古典というのは、他に例える術もなく矛盾して聞こえる。しかしながら、前回の小文をよんでいただければ、私の感覚も何となく分かってもらえるのではないかと思う。
さて、今回の話題は、まず、本の読了記録の話である。実は私は、中学2年の頃から読んだ本の記録を残している。と、言っても、途中の大半にあたる約18年間ほど記録がなく、また、本の題名と著者、日付のみをメモしたもので、感想が書いてある期間も数年間しかないような不完全なものだが、それでも、中2(1976年)~新入社員の頃(1989年)までの約12年間と、その後18年のブランクを経て、2007年以降今日までの約5年間の、合計17年間で延べ1,000冊余の本が表になっている。昔はルーズリーフの用紙に書いていたが、昨年、一念発起して、最初からの分を表計算ソフトで電子化しているが、電子化作業はまだ2010年あたりまでで、追いついていない。最近読んだ本は、相変わらず、ルーズリーフに題名を記録している。
何度か読み返した本も記録している点は、自分でも多少マメな性格かなと思う。2度目以降の場合は、書名、著者名、読了日の右に、2とか3とかの数字を書いておく。それで、今回、自分にとっての古典について書いている時、そうか!この読了記録の、読み返しの数字が一番多いものを探せば、それが自分にとっての古典なのではないかと思って、調べてみた。その結果、自分にとっての古典は、宮崎駿さんの「風の谷のナウシカ1~7」で、読み返し回数は5であった。
自分にとっての客観的な古典が、通常の本ではなく、マンガ本だったところが、自分らしい気もする。ちなみに、続きもののマンガは、例えば続きの1~7などをまとめて読了記録のNo.を1増やしている。私は、それほどマンガを読む方ではなく、ナウシカとか手塚治虫などの特定のマンガを除けば、読了記録の中のマンガ本は非常に少数派である。ちなみに、前回から話題の理科年表は、当然「読了」してないので、この一覧表には載ってない。
ナウシカは、現在高校2年の息子もファンで、高2にして、既に何度か読み返しているらしい。その意味では、親子2代に渡っての古典と言ってよい本であり、感慨深い。ちなみに息子は部屋にナウシカの2,000ピースのジグゾーパズルを飾ったりして、立派なナウシカファンである。表紙の絵を見るだけで、あの、久石譲さんの雄大な音楽が甦ってきて、またその世界に行きたくなる。これからも、いつまでも読み継いでゆきたい本である。
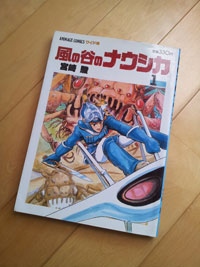
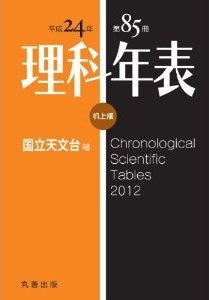

コメント