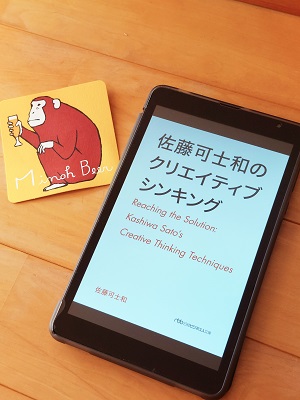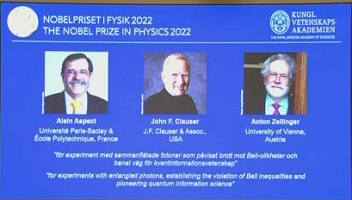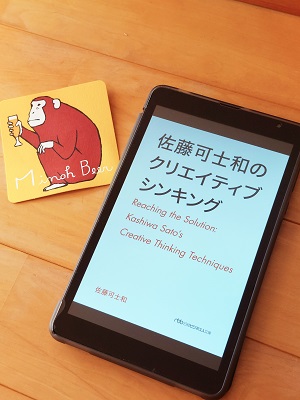
「佐藤可士和のクリエイティブシンキング」という本の中で、佐藤さんはプレゼンについて、こんな内容のことを言っている。若い頃は、見せ方の演出をしたり受けを狙ったり、肝心の内容よりうわべを気にして、表層的なテクニックにばかり気を取られていた時期があった。その後、優秀な先輩達の優れたプレゼンに触れて学び、経験を積む中で、現在では、中身を十分に考え抜いたうえで、シンプルに、自分がその問題に対して考えたきたプロセスを、順を追って率直にしゃべるだけというスタイルを身につけてきた。
つまり、プレゼンには中身があれば、見せ方はシンプルでよい、と言っている。あたりまえのような気もするが、プレゼンテーションという言葉からは、話の順番・ストーリーや、話し方、目線、態度、パワポに挿入するイラストみたいなことを想像しがちなところ、考え抜いた中身が良いプレゼンの本質であることを、改めて認識させてくれた。見た目より中身。
今迄の数回、チューリングテストでは、見た目が人間に見えるなら、AIは人間と言ってよいとか、ダックタイピングでは、ソフトウェア作りでは中身より見た目を活用することで良い作り方ができるとか、量子力学の「量子」に至っては、観測されるまではそもそも実在してない、つまり「中身」がないという話をしてきて、「中身」側が不利だなぁと思っていたが、佐藤さんの、やっぱり見た目より中身が大事という主張に、何かちょっと安心した気がする。
ただ自分も、職場では人のプレゼンを見たり聞いたりする機会が多少はあるが、せっかく中身があるのに、見た目をゴテゴテにしすぎたり、逆に、小説や学生のレポートのような文字だけのわかりくいものだったりするようなものも、いまだにあったりする。せっかく中身を考えたのなら、それにふさわしいシンプルで力強いメッセージを伝えられるようなセンスも、やっぱり必要だと思う。中身があることは前提だが、その上で、華美な見た目ではなく伝わる見た目、簡素すぎず見る側の立場に立った見た目も、やっぱり大事だと思う。佐藤さんの言うように、それが、中身をそのまま伝えられるような、透明な見た目を作れるようになりたいものだと思う。
2022.11.27.日 4回目のワクチンの副反応から復活
写真:Kindle本 on 8inchタブレットの表紙を撮影(自宅にて)