
暦の基礎は、太陽と地球の周期的な動きにある。1日は、人間にとっては太陽が昇って沈む周期だが、正しい定義は、地球が自らの中心軸の周りを1回転する時間のことである。また、1年とは、地球が太陽の周りを1周する時間のことを言う。では、1か月というのは天体の視点からはどういう時間のことだろうか?
月の満ち欠けの周期は約29.5日で、ほぼ1か月。この事実だけで、1か月という時間の単位が、月の公転周期をもとにして決められたことは疑いようがない。1年が12か月であるのは、地球が太陽の周りを1周する間に、月が地球の周りを12回周っていることを意味する。この12と言う数字は、ジャイアントインパクト(前回の記事参照)の際に、2つの天体が持っていた質量や運動エネルギー、それと衝突の角度によってほぼ決められたはずである。会社で開催される月例会議などというものの周期も、はるか昔の天体衝突の時に、その開催周期が決定されたのだと思うと、ちょっと感慨深い。
以前ラジオを聴いている時に、満月の日は、牛の出産数が、他の日に比べて有意に高いと言っていたことを思い出す。満月はおよそ月に1回、その時は単に神秘的な話だと思ったが、よく考えると、地球に生きる生物の特性が、月という天体の周期に影響を受けているとしても、それほどおかしなことではないと思うようになった。むしろ、当然なのではないだろうかと。
生物的なリズムという観点では、牛に限らず多くの哺乳動物で、排卵周期がおよそ1か月ということも興味深い事実である。一口に哺乳動物の排卵と言っても、大きく2種類あって、兎、猫、駱駝のように、交尾の刺激がないと排卵がおこらないタイプと、人、牛、犬のように、交尾と関係なく排卵が起きるタイプがある。後者のタイプの動物では、2種類のホルモン、卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)が排卵に関係しているが、このうち、黄体ホルモンが分泌されている期間(黄体期)は、多くの動物で2Wと一定しているそうだ。ヒトや家畜の排卵周期が4Wになっているのは、月経に1W,卵胞の発育に1Wとられて、合計4Wになっているためとのことである。
ここまで読んだ人の中には、もしかしたら、月の公転周期と多くの動物の排卵周期がほぼ同じなのは、単なる偶然だと言うかもしれない。しかし私には、生命に関わる重要な物質が、およそ2週間の周期で分泌される、という事実を、月の公転周期(=満ち欠けの周期とほぼ同じ)と無関係だと言う方が無理があると思う。月の公転周期以外に2週間と言う時間を説明できる合理的な理由は見当たらない気がする。「自然」について謙虚な感覚を持つ人なら、地球に生まれた生命は、その星の置かれた環境から影響を受けているはずだと考える方が、よほど理にかなっていると感じるだろう。
生命活動は、DNAに書かれている情報の物質化と、それに引き続く分子化学的な反応によって引き起こされる。排卵も、DNAに書かれた何らかの情報が、プロゲステロンを分泌する2週間と言う周期を決めている。生命進化の長い歴史の中で、命を生む重要な周期の情報が、地球の周りをまわる星の周期の影響を受けて記載されたと言われたとしても、驚くにはあたらない。
そんな実験ができるはずもないが、ジャイアントインパクトをやり直して、月の公転周期を60日にしたとしたら、多くの動物で、排卵周期は30日前後なっていることが確認できるのではないかと予想する。地球型惑星が多数発見されている昨今、そこに生きている生命のリズムが、衛星の公転周期にシンクロしている例もいくつか発見されることも予言しよう。もうすぐ55才となる身には、生きている間にそれを確かめることができない可能性の方が大きいけれど。ただ、複数の衛星を持つ地球型惑星もたくさんあるはずで、そんな星に住む生き物は、どんな周期で生きているのか、想像もつかず、ワクワク感は高まるばかりである。
2017.3.25(土)
写真:具満タンよりフリー画像
写真:具満タンよりフリー画像

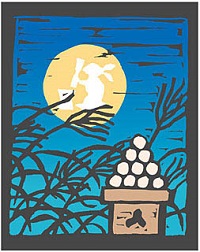

コメント