 カタツムリはゆっくり移動する、スローライフの師匠のような生き物だが、その殻はいつも綺麗で、汚れているところを見た事がない。もっとも、最近の都市生活者は、そもそもカタツムリと言う生き物自体、見た事がない人が多いかも知れないが。私が子供の頃は、梅雨時ともなれば、裏庭のあじさいの葉っぱにはカタツムリがゆったりと這っていたものである。そのカタツムリの殻は、水をかけるだけであらゆる汚れが流れ落ちて、いつも綺麗な表面を保っているそうだ。しかもカタツム君は、殻をつくる工場を持ってはいない。自ら食べた自然の素材を原料にして、かくも高度な性質をもった物質を静かに作り出しているのである。水で流すだけで油汚れなどをよせつけない表面をもつ物質を、自然に負荷をかけることなく作りたいと思ったら、カタツムリの殻に学ぶしかない。
カタツムリはゆっくり移動する、スローライフの師匠のような生き物だが、その殻はいつも綺麗で、汚れているところを見た事がない。もっとも、最近の都市生活者は、そもそもカタツムリと言う生き物自体、見た事がない人が多いかも知れないが。私が子供の頃は、梅雨時ともなれば、裏庭のあじさいの葉っぱにはカタツムリがゆったりと這っていたものである。そのカタツムリの殻は、水をかけるだけであらゆる汚れが流れ落ちて、いつも綺麗な表面を保っているそうだ。しかもカタツム君は、殻をつくる工場を持ってはいない。自ら食べた自然の素材を原料にして、かくも高度な性質をもった物質を静かに作り出しているのである。水で流すだけで油汚れなどをよせつけない表面をもつ物質を、自然に負荷をかけることなく作りたいと思ったら、カタツムリの殻に学ぶしかない。
サバンナ地方に住むシロアリは、昼の外気温50度、夜は0度と言う過酷な寒暖の差のある場所に、大きなものでは6~7メートルにもなる巨大な土の巣を作るが、その巣の中の温度は、ぴったり30度に制御されているということである。電気もガスもなく、エアコンを取り付けるわけでもなく、全て自然の素材で快適な住環境を作り上げているシロアリの知恵。彼らが快適な環境で生活するために支払っている環境負荷は、人間がエアコンで消費するエネルギーに比べれば、ほとんどゼロである。人間はシロアリに弟子入りして、その高度な技を謙虚に教えてもらうべきである。
石田秀輝さんという方がいる。一般向けの著書として、「自然に学ぶ粋なテクノロジー」(化学同人)と言う本を書かれた方である。この本は、ネイチャーテクノロジーを易しく解説した本で、私も手元に置いて愛読している。上に挙げたカタツムリとシロアリの話は、同書に紹介されていた例である。この本には、その他にも様々なネイチャーテクノロジーの具体例が掲載されている。
ネイチャーテクノロジーとは、石油という有限な資源を人間の都合の良いように加工したり、エネルギーを取り出したりする、いわゆる人間中心で、自然ないがしろ型のテクノロジーからの脱却をめざす。そして、自然が持っている優れた性質、それは生物を動かしている極めて効率の良いエネルギー変換や、自然の持つ完全な循環のあり方のような、自然の持っている知恵の具体例に学びつつ、新しいテクノロジーを生み出して行こうという取り組みである。石田さんは、その活動の先頭で活躍されている方である。
現代文明が向いている方向が環境問題の根本的な問題だという意味において、環境問題は、現代社会の文明の問題と同義である。その文明の方向を変えていこうと言うのが、ネイチャーテクノロジーの基本的な考え方だと理解した。良くも悪くも、現代文明は、テクノロジーやサイエンスが先導してその方向を決めているのであるから、その根本的なテクノロジーのありかた、考え方を、自然から学び、自然を中心にしたものに変えいこうということである。
ネイチャーテクノロジーに関しては、赤池学「自然に学ぶものづくり」(東洋経済新報社)、Janie M.Benyus「自然と生体に学ぶバイオミミクリー」(オーム社)、志村史夫「生物の超技術」(講談社ブルーバックス)などの書籍があるが、まだまだ数は少ない。
子供の頃、理科の授業で、光合成のことを学んだとき、太陽エネルギーを人工的に取り出すことのできるような光合成工場を作ればよいのに、と思ったことがある。長らくそんなこと忘れていたのだが、ネイチャーテクノロジーについて学ぶうち、昔のことをふと思い出した。その時の想いを忘れずに持ち続けていたら、今とは違った人生を歩んでいたかもしれない。
2010.3.4(木)

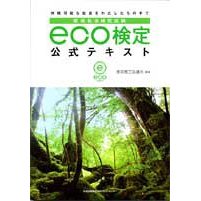

コメント