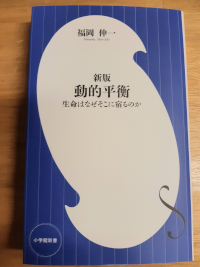
生物学者の福岡伸一さんが書かれた、「動的平衡」という著書がある。初版が出たのが2009年で、その頃、「生命とは、動的平衡にある、”流れ”である」という考え方がとても新鮮で、知的にワクワクしたことを覚えている。生命とは何かという問題は、色んな人が色んな立場から探求していて、DNA、分子生物学、計算機の分野での人口生命、ロボット、原始地球での生命誕生、宇宙からの飛来説、地球外生命体、中村桂子の生命誌など、アプローチの方向は限りがない。そんな中で、福岡さんの言った「動的平衡」というキーワードは、生命の本質を表現する言葉として、とてもしっくりくる。
最近、考えるネタとして話題にしてきた、方丈記の冒頭を改めて読んでみたときに、この、動的平衡というキーワードに直結していることに気がついた。改めて冒頭の部分を抜粋すると、
「行く河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。淀みに浮かぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例なし。世の中にある、人と栖と、またかくのごとし。」
まさに、動的平衡を表現した、簡潔だが適確な真理を言っている。長明さんの脳裏にあったのは、京都という街を形作っている家や軒並み、そこに住む人であって、街は変わることなく続いているものの、そこにある家や人は、常に入れ替わっていて、河の流れに浮かぶ泡のようにはかない、ということを言ったものなので、生命が流れであると言ったわけではない。でも、自分には、個々の家や人は泡のように消えては現れるが、街の姿は、河の流れのように連綿と続いている、生命のようなものだと言っているように読める。
しかも、河に浮かんでる泡の例えは、世の中の人も同じだと言っている。拡大解釈を承知で言えば、人間も、同類の生命も、それを構成する物質(泡)は常に入れ替わるが、生き物(河)は平衡を保って存在する、という真理を、800年前に生きた数寄人が見抜いていたと言っても、反対する人はいないだろう。でも、多分自分が思いついたようなことは、とっくに色んな人が気付いているのだろうな、と思いつつ、こんな気づきの元ネタになってくれる古典って、やっぱりいいなと思う。
2019.12.22(日)
写真:動的平衡(小学館新書)の表紙
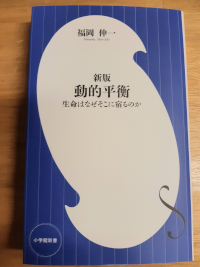


コメント