
2019.3.9の朝日新聞の折々のことばというコーナーに、鯨の解体職人さんが言った、こんなことばが載っていた。「包丁で切るのではなく、包丁に切らすっていうのは、むずかしいのさ。」この、”包丁に切らす”という言葉が気に入って、いつか紹介したいと思っていたので、今日、書いてみる。
鯨の解体というのは、見たことがないので想像するだけだが、ちょっと考えただけでもたいへんそうである。自分の体より大きな、タンパク質や脂肪や骨の塊を、包丁で切って、持ち運べる、あるいは食べられるサイズに切り分ける作業。体力だけでなく、鯨の体の構造に関する深い知識と、食べ物としての鯨肉の知識、そして、何より、包丁を使うセンスが要求される仕事だろう。初心者がやったら、3日かかって、くたくたに疲れる作業を、腕のよい職人さんなら、半日で、楽々と質の高い仕事をしてニコニコしているのだろう。
そんなたいへんな作業だからこそ、無理に切るのではなく、包丁が勝手に動いて、キレイに切ってくれるような感覚を得られたら、それは、道具とそれを使う人が一体となった、すばらしい境地のように思うのだ。その新聞記事では、そのような感覚を身につけるのに、10年かかると書いてあった。10年毎日修行しても、身につけらるかどうかわからない。筋がよくて、つらくてもその仕事が好きで努力できる人だけが到達できる境地のように思う。
もう10年前に、この道具考で、テニスラケットが腕の延長だと書いたが、鯨職人にとっての包丁も、テニスプレーヤーにとってのラケットと同じように、完全に腕の延長なのだろう。しかも、自分が切るのではなく、包丁が切ってくれるというのだから、もしかしたら一流のテニスプレーヤーも、自分がボールを打つのではなく、ラケットが打ってくれるような感覚を持っている人もいるのかもしれない。私の小文に時々登場いただいているロジャー・フェデラー選手は、見ていると、ボールが相手のいない場所に勝手に飛んでいくように見えることもある。
もう少し想像力を働かせると、包丁が切るというよりも、鯨の肉が、包丁をあてることで、勝手に切れてゆくような感覚でもあるのではないだろうか。そこには、対象と自分しかなく、腕も包丁もない。多分、思い通りの仕事ができる職人さんは、そんな感覚を持っていそうな気もする。モーツアルトが、短時間に多量の名作を作曲できたのは、曲が頭の中で既にできていて、ペンが勝手に動いて譜面が出来上がったに違いないと、以前何かの本で読んだ。出来上がりのイメージが明確にできていれば、どんな角度でどの程度の力で包丁を動かせば鯨肉が切れるのか、考える必要もなく、何の無理も無駄もなく動かせるのだろう。それを、包丁に切らす、と表現したのだと想像する。
自分のつたない文章も、そうありたいものだと思うが、まだまだ、思い通りに書けるには程遠い。パソコンのキーボードが勝手に書いてくれるような境地には、10年たってもなれそうもない。何度も書いては直す繰り返し、でも、それも、また楽しむことが、ちょっとでも包丁に切らす感覚に近づくと信じて、今年もまた、ぼちぼちと、思いついたことを書き残してゆくことにしよう。
2020.1.1(水)
写真:モーツアルト WikiPediaより

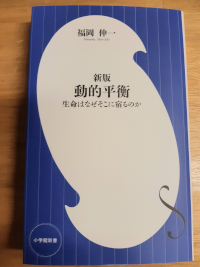

コメント