
ものには名前がある、そんなの当たり前だって?本当にそうだろうか。空を飛ぶ鳥には、「ツバメ」とか「すずめ」とか名前がついているじゃないか、と言うかもしれない。でもそれは鳥の種類の名前であって、眼の前を飛んでいった、その鳥の名前ではない。中にはペットとして飼っている鳥に、Q太郎などという名前をつけている人もいるかもしれないが、そうでない限り個々の鳥に名前はない。
鳥ならまだわかりやすいが、例えばウィルスのようなモノや、岩石のような無機物はどうだろうか。岩石は稀に、夫婦岩などの名前がつけられることもあるが、地球を構成するほとんど全ての岩石には、玄武岩とか安山岩などの種類の名前はあっても、個別の岩には名前はない。ましてやウィルスの1個1個に名前など付けられようはずがない。この世界には個別の名前を持たないもののほうが圧倒的に多い。
そう考えると、名前というのは全く人間の都合で、識別する必要の有無で付けたり付けなかったりされるものだとわかる。人や飼い犬のように、個体を識別する必要があるものには個別の名前を付け、種類だけわかればよいものには種類の名前を付ける。名前とは、本質的にあるものではなく、人間の営みが前提で存在する。だから、木星という惑星は人間がいなくても存在するが、木星という名前は人間が名付けない限り存在しない。名前のないただのガスの塊なのである。
逆に言うと、人間の知性は、名前と本質的に結びついている。何かを識別する必要から名前が必要で、それが言葉の始まりだったのだと想像する。日本列島にホモサピエンスが住み始めたのは、今から4〜5万年位前だと言われているが、その頃の人は、食べられる木の実や、危険な動物を識別する必要があったはずだが、それらをどんなふうに呼んでいたのだろうか?まだドングリを表す言葉はなかったのだろうか?でも、その頃には、今、右手に持っているドングリと、左手に持っているドングリは別のものだけど、それぞれに名前はついてないよなぁなどと考えるような、変な古代人は、きっといなかったのだろうな。
2021.1.4(月)
写真: 夫婦岩・伊勢 Wikipediaより

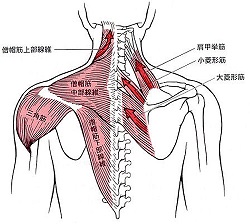

コメント