 量子力学で、今もわかってない基本的な問題の1つに、波束の収束問題がある。量子力学で扱う粒子は、観測するまでは空間的な広がりを持っていて、存在確率の空間分布(確率波)でしか記述できないが、観測した途端に、一瞬にして観測したその1点に収束することになるが、それはなぜか?という問題である。
量子力学で、今もわかってない基本的な問題の1つに、波束の収束問題がある。量子力学で扱う粒子は、観測するまでは空間的な広がりを持っていて、存在確率の空間分布(確率波)でしか記述できないが、観測した途端に、一瞬にして観測したその1点に収束することになるが、それはなぜか?という問題である。
この、確率波の不自然な挙動は、量子力学のコペンハーゲン解釈と言われ、量子力学の成立当初から、それ以上立ち入ることのできない、言わば原理として扱うしかない自然の性質だと考えられてきた(不正確かもしれないが概ね)。それは、疑問ではありつつも、量子力学の理論が、実験結果と高い精度で一致するという信頼性の高さから、解釈はどうあれ、自然はそう振舞っているのだし、今の人類の科学認識では太刀打ちできそうもないし、そういう意味で原理として扱われてきたものだ。
物理学者でさえ持て余していたこの自然の不可思議さを、自分も、長年楽しめる知的興味として持ち続けてきたが、先日、本屋で立ち読みしていたら、この問題を扱った一般向けの本を発見して、おぉ!と思った。それは、H.C.フォン・バイヤーさんの「QBism 量子×ベイズーー量子情報時代の新解釈」という本だった。その本によれば、量子力学の扱う確率を、ベイズ統計と解釈すればいろいろわかることがある、と言っていた。
ベイズ統計?どこかで聞いたことがある、と思ったら、機械学習の基礎理論で使われていたと思い出した。それで、少し調べてみると、ベイズ統計とは、新たな観測事実を得る度に、ある事象に関する確率を、その事実が観測されたことを踏まえて更新する、と言う考え方に基づくものであった。それは、確率を、何度観測を繰り返しても変わらない普遍的なものと捉える、古典統計と対比されるもので、言わば帰納的な確率を扱うものである。今のAIはビッグデータを入力としてニューラルネットの重みを更新するという単純な(というと言いすぎだろうが、まぁ)しくみなので、観測事実で確率を更新するというベイズと相性がよいのは感覚的によくわかる。
確かに、観測される前には空間的に広がっていた確率を、観測事実によって1点に存在するという観測後の確率に更新する、と言われれば、ちょっとだまされたようでもあるが、まぁ、そういうものか、とも思えて、自分なりに何かスッキリしたように感じた。波動方程式は観測される確率のことしか言ってないので、観測されたらその確率は修正されるべきもの。シュレディンガーの猫も、観測されるまでは生死は確率、で何の問題もなくなる。
以前自分が昔書いた、このコラムの帰納の時代4題を今更ながら読み返してみた。(帰納の時代を読んでない人は、ここでカテゴリーを選んで読んでみてね。)民主主義も歩くことも、岩瀬投手も、イタリヤ料理もインターネットも、世の中帰納の時代と確信していたところに、自然よ、やっぱりおまえもそうだったのか、とちょっと嬉しくなった。結局のところ、自然も、日々自らを確かめつつ成り立っている帰納的な存在である。ベイズ統計、いいんじゃないか。新たな観測事実によって日々変わってゆく帰納的な世界、それが世界の正しい認識のしかただと思う。
写真:QBismの和訳本の表紙

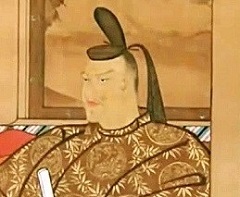
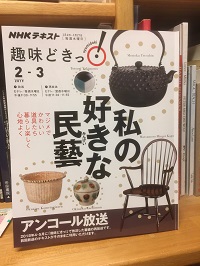
コメント