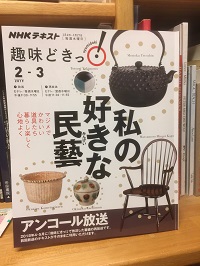
民芸がちょっとしたブームになっているようだ。いつも聴いているラジオの教養番組で、民芸の話題が取り上げられていたし、本屋でも、NHKテキストのコーナーで、「私の好きな民藝」というテレビ番組のテキスト本を見かけた。その本の冒頭で、民藝案内人の鞍田崇(くらたたかし)さんが、こんなふうに言っている。近年、自分の暮らしを自分にとって心地いいものにしようという機運が高まっていて、そんな流れから民芸に再び脚光があたっている、と。
自分の暮らしを自分にとって心地いいものにする、これは、私にとっては自分の暮らしのQOL(Quality of Life)を上げること、と読めた。日常の暮らしを大切にして、心豊かに暮らすということ、民芸とは、QOLを上げること、と言い換えてもよい。
ここで出てくる民芸の主役は、食器、花器、鉄瓶、籠、織物、木工品など、いわゆる職人の手仕事で生み出されるものである。本で紹介されていたものは、写真で見ただけでも美しく、もし自分の暮らしの中にこんなものがあって、使ったり、眺めたりできたら、ほんとに心豊かになれそうなものばかりだった。盛岡の南部鉄器の写真など、見ただけで新幹線に乗って、かの地へ旅立ちたくなった。
現代の暮らしを心地よくするものの代表と言えば、PCやスマホと答える人も多いのではないだろうか。これらは、工業製品であり、民芸とは対極にあるもののように思われるかもしれない。しかし、PCやスマホの本体は、ソフトウェアであり、ソフトウェアは、いまだに機械で作るに至っていない、手仕事の領域のものと言ってよく、その意味で民芸に通じるところがある。特に、日々使うエディター(プログラムやテキストを書くためのソフトウェア)などは、「手に馴染むエディター」と言う表現がしばしば使われる通り、どれだけ心地よく使えるか、がエディターを選ぶときの基準になる。それは、花瓶を選ぶときに、部屋に置いてどれだけ暮らしを心地よくするかを基準とすることと、とても似ていると思った。
ただ、ソフトウェアには、大きく分けて2種類ある。1つはWindowsのように、1つの会社が自らの事業のために作っていて、原則としてソースコードが公開されていないプロプライエタリソフトウェアと呼ばれるもの。もう一つは、Linuxのように、原則としてソースコードが公開されていて、会社に限らず、世界中の多くの人の手によって作られているオープンソース・ソフトウェア(以下OSS)である。職人の手作り感を感じるのは、オープンソースであり、良質なOSSを使うときに感じる豊かさは、良質な職人の手で作られた茶碗を持った時に感じる豊かさと通じるものがある。
どちらが勝れていると言うつもりはない。Windowsはビジネスの世界では広く使われていて、信頼性があり、会社ではほぼ全員がウィンドウズのPCでメールを送ったり、表計算ソフトで資料を作ったりしているし、もちろん私も毎日使っている。でも、こういった文章を書いたり、自分の書斎で使うPCは、良質なOSSを使いたいと思うのだ。WindowsもLinuxも(Macも)、機能的にも見た目も、ほとんど違いはないじゃないか、と言う人もいるかもしれない、でも、気は心、職人の手仕事的な匂いを感じる、”Linux Mint MATE”(マテ)などを、ちょっと古いPCに淹れて、最近手に馴染んできたエディター”VSCode”を開いて、丁寧に暮らすことに思いを馳せながら、この小文を書いている。
2019.2.4(月)
写真:NHK趣味どきっ 2019 2-3月号 テキスト「私の好きな民芸」
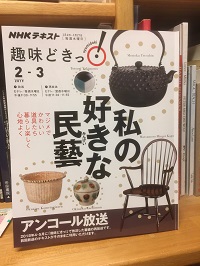

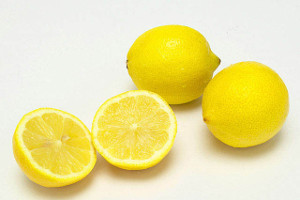
コメント