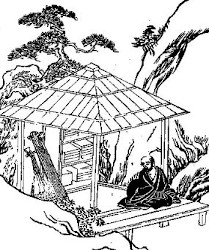
長明さんは六十才で京都の南、日野の山里に約3メートル四方(四畳半程度)の小さな庵を作って、そこに住み、21世紀に生きる私達が読むことのできる有名な古典、「方丈記」を書いた。その小屋住まいに至った動機の一つとして、小さいので土地を購入する必要がなかった、と書かれている。これは、公共の場所(あるいは他人の土地)に、勝手に小屋を作っているようなもので、現代では聞こえはあまりよくないが、平安末期はそんなせちがらくはなかったのだろう。もしそこで気に入らないことが起こったら、さっさと小屋を解体して、別の場所に引っ越すことができることが、方丈ライフを選んだ理由だと言っている。これはある意味、とても合理的ではある。
初期の縄文時代の集落は10人程度以下で共同生活する集団のサイズだったというが、その主な理由は、近くの集落と争いが起こった時や、ゴミの捨て場所がなくなってきたとき、あるいは近くの山で採っていた木の実や猪などの獲物が減ってきた時など、別の場所に移住することで問題が解決できる利点が大きかったためだったとのことだ。大きな集団で1箇所に定住すると、移動という単純で強力な解決策を採れないため、隣の集団との複雑な利害の調整や紛争解決、ゴミを処理するための技術開発(土木工事のような)、食料確保のための工夫(実のなる木を植える、狩りの道具の改良)など、様々なことにチャレンジしないといけなくなる。
現代社会でも、あえて定住する家を持たないライフスタイルを選ぶ人がいる、という話を新聞で読んだ(中日新聞2019年1月5日、エイジングニッポン6「モノも職場も持たない生活」)。そこで紹介されていたのは、寝起きのできる大型の車(バン)を住まいとして、都心の駐車場に住み、ウェブデザイナーとして、個人が共同で使えるシェアオフィス(駐車場から徒歩10秒!)で働く人の話である。余分な荷物は収納サービスに預け、風呂はホテルのジムなどを利用する、「寝床以外は全てシェア(共有)。満員電車で長時間通勤し、苦労して高い家賃を払う生活がばかばかしくなった。」と言う。ネットとパソコンがあれば仕事ができるので、気が向くままに職場(シェアオフィスのような場所)を決め、神戸市で仕事をした時は、淡路島で釣りを楽しんだとも。モノを持たずにシェアする時代、その最先端のライフスタイルだと感心した。
長明さんの方丈のことを考えていた時、このバンライフの人の「バン」が方丈と重なった。事実、長明さんは庵を作るための部材を、荷車2台で現地まで運んで自ら組み立てたと言う。その荷車はバンとよく似ている。結局、長明さんは、日野から移住することなく、その地で生涯住んだとのことだが、それは、水も食べ物も燃料(薪)も近くにあり、一人の生活ではゴミが大量に出ることもなく、近くに迷惑な人も居らず、当初想定したような引っ越しを余儀なくされる事態に出くわさずに済んだということだろう。
もしかしたら、小さい家はすぐ引っ越せるからチョー便利だと言ったのは、長明さん一流の負け惜しみだったのかもしれない、とも思う。方丈記全体からは、昔は権力も財力もある家の息子として大邸宅に済んでいたが、次第に没落して小さい家に移り住み、最後は方丈だと、半ば自虐的に聞こえるような書き方をしているような箇所もある。でも、そこに書かれている身軽さ、しぶとさは、平安時代末期と言う、世の中が大きく変革する時代にあって、何かと騒がしく地球全体が激動期に入っている、令和の現代に、バンライフに挑戦している若者の姿と通じる何かを感じる。
片方は方丈の庵で、仏への祈りと楽器の演奏、トレッキングなどを楽しみながら自給自足した老人、もう片方はネットとパソコンを業とし、モノを持たず、気の向くままの自由さで世の中と渡り合っている若者。この老人は、若者の遠い祖先のようにも思えるのだ。
2019.7.5(金) 有給休暇で1日休み。のんびりとPCのキーボードを叩く。
写真:方丈の庵(扶桑隠逸伝)
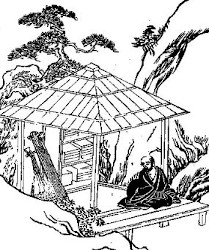


コメント
[…] 昨年、「方丈記を読む・その3〜モバイラーの先達 長明」で、モノを持たずに大型の「バン」で、都会の駐車場に暮らすウェブデザイナーの話を書いたことがあるが、彼などは生活のほぼあらゆるものがシェアやレンタルで、その人生そのものも、天から授かった時間をこの世界に貸し出して生きているような気がして、何かとても新鮮な生き方のように感じた。そのバン生活が、長明さんの方丈生活と似ていると思って、そんな文章を書いた。 […]
[…] そう言えば、このコラムの中でも「方丈記を読む・その3~モバイラーの先達 長明」の中で、縄文人の集落の移動について書いていたことを思い出した。近くの集落との争い、ゴミの捨て場所、獲物の数などの問題を解決するための最も簡単な方法が「移住」だったという説で、それも、もともと人類がアフリカから出て、より住みやすい土地を目指して旅の途についた前歴のある種族であることを思えば、何も縄文人だけの特質と言うわけではなく、ホモ・サピエンスの持つ性質だったというだけのことだろう。 […]