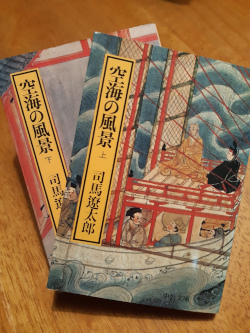
司馬遼太郎さんの「空海の風景」を初めて読んだのはずいぶん昔のことだが、最近もう一度読み返す機会があった。今から1,200年も昔に生きていた人だが、司馬さんの手にかかると、まるで目の前を空海さんが駆け抜けたような、妙に生々しい人間空海が文字の間から現れてくる。
言葉で伝わることと伝わらないことを考えていたとき、この物語に出てくる、空海と最澄の関係に思い至った。空海と最澄は、西暦804年に同じ船団で、遣唐使として唐に渡った。空海は当時無名の僧だったにもかかわらず、密教の正当な後継者として、大阿闍梨恵果(けいか)和尚から密教の奥義を全て授けられ、大量の仏具と密教経典を日本に持ち帰る。一方最澄は、当時無名だった空海とは違い、国費留学のエリート僧として唐に渡り、当時の正当な仏教として天台宗を学んで帰国する。当時、既存の仏教とは一線を画した最先端の教えとして、密教が流行になりつつあった。最澄は、無名だった空海が唐で得たものの大きさを理解できた上に、まじめで謙虚な人だったので、空海に密教の経典を貸してほしいと頼み、更に、灌頂(かんじょう)して欲しいと頼みに行く。灌頂とは、密教の有資格者として認める儀式のことである。ここからが、言葉で伝わることと伝わらないことの本題になる。
空海は、密教の本質は、修行や儀式を通して、身体や超自然的な感覚で身につけるものであって、文字や言葉で伝えるものではないと信じていたので、最澄の頼みは、とても受け入れられるものではなかった。一方、最澄は、仏教の教えは、経典に書かれたことを読み込んで理解すれば習得できるものだと思っていた。歩み寄れない2人の感覚の違いである。もともと、空海は、唐に渡る以前の若い頃、青春時代を四国の山岳地帯を歩き回って修行し、厳しい自然から、自らの身体を通した修行で独自の思想を身につけ、それがベースとなって、唐に渡ってから短期間で恵果和尚から見出される人材となった。最澄は、学問エリート僧で、そんな生きるか死ぬかの肉体修行などで仏道を理解できるとは思ってない。話が合わなくて当然である。密教の教えは、言葉では伝えられないと思っていた空海、思想は言葉で伝えられると思っていた最澄、1,200年前、奈良から平安へ時代が切り替わる時、日本仏教の2人の巨人が、言葉で伝わることと伝わらないことを巡って対立していたのである。
空海の風景を最初に読んだのは、長女が生まれた翌年、31歳のときなので、今から27 年も昔のことだが、その時は、人間臭い空海がとても魅力的に思えて、頭はよいが身体感覚で身につける感覚がわからない最澄は、この物語の中では空海の引き立て役のように描かれているように見えた。しかし、昨年、2度めに読んだときには、空海の底知れない超人的な能力と、自分こそがナンバーワンだという自信が、アクの強さと生意気さに映って、今ではあまり好きになれなくなった。尤も、これは、司馬さんの描く空海と最澄の描像についての感想なので、それが彼らの真の姿だったのかどうかは今となってはわかりようがないのであるが。
司馬さんの小説を読むと、1,200年前を生きた人が、目の前で息をしているように感じる。その意味で小説の中の言葉たちは、時を超えて、映像以上のものを伝えられる力を持っていることを証明している。この小文のタイトルは、言葉の限界としたのだが、良質の小説は、言葉の力に限界がないことを教えてくれる。
2020.7.3(金)
写真:空海の風景(自宅にて撮影)
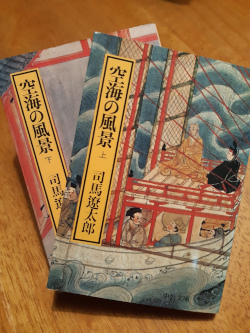


コメント