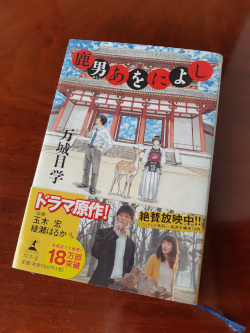
先日、ふと見ていたTVで、松本清張のドキュメンタリー番組をやっていて、清張さんの「天城越え」という小説が、川端康成の「伊豆の踊子」を意識した、言わば対抗作品だということを紹介していた。伊豆の踊り子では、主人公はエリートの若者で、相手は清純な踊り子、一方天城越えでは、主人公は貧しい鍛冶屋の息子、相手は娼婦と、あえて真逆の設定で、天城トンネルを越える方向も逆になっている。これは、川端康成がノーベル文学賞を取った文学界の重鎮、松本清張は、ベストセラーを書いてはいたが庶民の目線を大切に思っている市井の作家という意識が、こういった対抗意識を生んだのではないかと解説していた。
昔の作品を下敷きにしたり、題材にしたりすることは、文学の世界ではむしろ当たり前なのであろう。ずいぶん昔に読んだ小説だが、万城目学の「鹿男あをによし」という作品がある。主人公が東京から奈良の高校に赴任して、いろいろのっぴきならない事情に巻き込まれながら人間的に成長してゆく物語だが、これは、夏目漱石の「坊っちゃん」の設定とよく似ていて、明らかに坊っちゃんを下敷きにしている。鹿男は、坊っちゃんを知らない人でも十分楽しめる作品ではあるが、坊っちゃんを知っている人には、より楽しめる作品となっていると思う。ちなみにこの小説、2008年に、玉木宏と綾瀬はるかのキャストでドラマ化されて、家族で楽しく見た記憶がある。
文学の世界では、そんな例は山ほどあるのだろう。特に、和歌では、本歌取りは、過去の有名な作品の世界を下敷きとして取り込むことで、新たに作られた作品の味わいがより深くなる効果がある。俳句より長いとは言え、たった31文字で心が動いたことを表現したいと思った時、過去の有名な歌人が詠んだ豊かな世界を、自分が表現したい世界に付け加えられるのなら、とても効率がよい。31文字を最大限に活用するのに最適な手法だろう。
ミームとは、Wikipediaでは、「脳内に保存され、他の脳へ複製可能な情報で、例えば習慣や技能、物語といった社会的、文化的な情報である」と定義されている。人が考えたことで、文学や芸能あるいは社会習慣や社会のしくみなど、時を超えて伝えられる、言わば社会的、文化的な記憶のことである。上で挙げた例で言うと、漱石のミームが万城目学に引き継がれている、と言うことになろうか。良い文化の記憶を、ミームとして伝えてゆくことも、文化人としての使命だと思う。
2021.5.23(日) 例年より早い梅雨入後、久しぶりの気持ちの良い晴天の日
写真:万城目学「鹿男あをによし」表紙の写真:自宅にて撮影
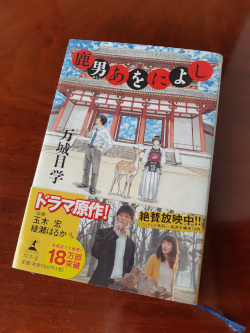


コメント