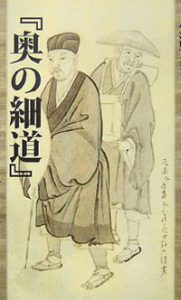 世界的に有名なウォーキングコースと言えば、ドイツ、ハイデルベルクの「哲学者の道」であろう。カントやヘーゲル、ゲーテやショパンと言った、超有名な偉人たちが好んで歩いたといわれるこのウォーキングコース、写真で見る限り景色も美しく、哲学や芸術の思索を深めるのにはもってこいの道のように見えるのだが、実際に歩いた人の感想が書かれているウェブのページなどを見ると、意外とキツイ山道らしい。この道を、偉大な哲人や芸術家が、どんな姿勢、どんな歩き姿で歩いていたのか、物凄く興味がある。
世界的に有名なウォーキングコースと言えば、ドイツ、ハイデルベルクの「哲学者の道」であろう。カントやヘーゲル、ゲーテやショパンと言った、超有名な偉人たちが好んで歩いたといわれるこのウォーキングコース、写真で見る限り景色も美しく、哲学や芸術の思索を深めるのにはもってこいの道のように見えるのだが、実際に歩いた人の感想が書かれているウェブのページなどを見ると、意外とキツイ山道らしい。この道を、偉大な哲人や芸術家が、どんな姿勢、どんな歩き姿で歩いていたのか、物凄く興味がある。
生涯に渡って規則正しい生活を送ったと言われている大哲学者、カントについては、その独特のウォーキングの習慣について、有名な逸話がある。カントは毎日決まった時刻に決まった道を散歩し、その時刻が極めて正確であった。そのため、散歩の道沿いにある家では、カントが通るのを見て、自宅の時計の時刻を修正したと言うことである。本当であれば、相当に変わった人であったように思う。私は哲学に詳しいわけではないが、カントと言えば、あの重厚な認識論哲学を作り上げた人。その巨大な仕事は、物凄く几帳面な生活の中から1歩づつ積み上げられたものであったのだ。多分、歩く姿、足の運びも、軽々しいステップなどではなく、1歩づつ踏みしめるような歩き方だったに違いないと想像する。
日本にも、「哲学の道」と名づけられた有名な散歩道がある。洋の東西を問わず、哲学と散歩道には深い関係があるらしい。京都、南禅寺から銀閣寺に至る、京都疎水という水路沿いの美しい小径である。こちらも有名な哲学者、西田幾多郎が日々ウォーキングしたことで有名であり、写真を見ると、桜の春、紅葉の秋は言うに及ばず、夏も冬も格別の風情がある。写真だけでも十分美しいのだが、実際に歩けばいろんなインスピレーションが湧いて来そうである。私も若かりし頃、一度訪ねたことがあるが、その頃は歩くことに特別な興味もなく、特別な印象も持たなかった。今行けば、もっと様々に感じることもありそうで、ぜひまた訪ねて、自分の足で歩いてみたい。
歩くことが特別な意味を持っていた偉人と言えば、宮沢賢治を思い浮かべる。賢治は強い向かい風に向かって歩くのが好きで、歩きながら詩や童話の着想を得たりすると、奇声を上げて飛び上がったりした、という話を聞いたことがある。あの有名な、”アメニモマケズ、カゼニモマケズ”の詩も、そんな向かい風に向かって歩きながら、全身で歩く力強い感覚から生み出されたと思うと、文字だけからでなく、その行間に、生き生きとした力強さを感じる。きっと宮沢賢治は、頬や腕や胸にいっぱいの風を受けて、足の裏全体で地面を感じながら歩いたのだろう。
そう言えば、日本には、松尾芭蕉と言う、歩きの達人とも言うべきウォーキングの師匠がいるではないか。奥の細道では、江戸から、奥羽・北陸・大垣に至る、約2,500Km近い道のりを歩き、偉大な俳句を多数残した。芭蕉は江戸時代の道を、一体どんな姿勢で、どのぐらいの速さで、どんな呼吸をしながら歩いたのだろうか。
その他にも、まだまだ、歩くことと関係の深い有名人は多い。アインシュタインも毎日、勤務先の研究所まで歩いて通勤したというエピソードを読んだことがあるし、弘法大師空海も修行時代には険しい山道をひたすら歩いたことだろう。日本地図を作ったの伊能忠敬も、長距離ウォーキングの先生にふさわしいし、釈迦も布教活動のために、インドの広い範囲を歩いて旅している。これらの偉人たちがどんなふうに歩いていたのか、できることならタイムマシンを借りて、この目で見てみたい。そんなことに思いを巡らせながら、日々ウォーキングを楽しんでいる。
2009.11.29(日)
写真:小澤克己著「奥の細道」新解説(東洋出版)表紙より
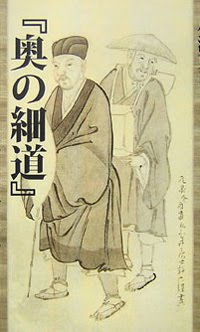
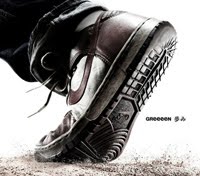

コメント