
先日見たTVで、NHK交響楽団のスペシャル番組をやっていた。歴代のN響指揮者の名演奏をちょっとづつ紹介するという番組で、ノイマンとかマゼールとか、有名な指揮者の昔の映像が出て、思わず見入ってしまった。最近、スマホに入れている音楽は、KennyGとか小野リサとか、リラックス系の音楽が多くて、久しくクラシック音楽を聴いてなかったが、クラシックもいいなと思った。特に、番組の最後に演奏された、ズービン・メータの第九は、震災直後に被災者に贈られた演奏だったとのことで、指揮者も演奏者も観客も一体となった祈りが伝わってきて胸が熱くなった。
日本では、なぜか毎年年末になると繰り返し演奏される、第九という曲を聴きながら、これが本当のクラッシックというものだと実感した。多くの人がいいと思って繰り返し演奏され、繰り返し聴かれる音楽。この曲、最初に発表されてから、世界全体で、一体何億回演奏されたのか、想像もつかない。同じ曲が、何度も、多くの人の手で奏でられ、多くの人の耳で聴かれ、多くの人の心に何かを残す。指揮者によって、演奏者によって、ホールによって、その日の天気によって、そして、演奏される動機や世情によって、表現されるもの、伝わるものが違ったものになる。しかし、その良さは時を超えて普遍なもの。そう思うと、前回取り上げた、Timeless Wayと重なった。
アレグザンダーさんがパターンとしてまとめたものは、建築や街の「クラッシック」な要素であった。住まいや街をアートだとすれば、人々によって繰り返し実現されてきた心地の良い表現、それがデザイン・パターンであり、良いものとして親しまれるものと言う意味で、クラッシックと同義であると気付いた。
最近、ほぼ日の河野通和さんが始めた、古典の学校のページを見た。この混沌とした時代に、昔から繰り返し読まれてきた「古典」の価値をもう一度、そして何度でも、深く会得して、現代をちゃんと生きる指針にしよう、という趣旨なのだと理解した。古典は、昔から何度も繰り返し読まれ、親しまれてきた書物。これもまた、Timeless Wayである。
アレグザンダーのTimeless Wayと、メータの第九と、河野さんの古典が、自分の中で「なりよい」ものの在り方に収斂した。それで、もっとクラッシックに親しみたいと思った。何より、自分がなりよく生きるために、そして世の中を少しでも住みよく、なりよいもにするために、皆さん、もっと古典に親しもう!
2017.10.8(日)
写真:ズービン・メータさん(Wikipediaより)

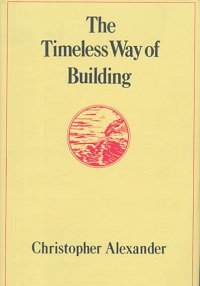
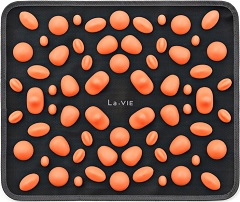
コメント