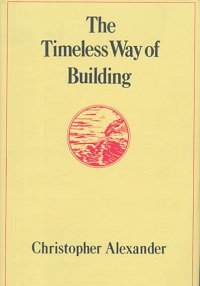
クリストファー・アレグザンダーさんは、建築家だが、パターン・ランゲージという考え方を提唱したことで知られている。”The Timeless Way of Building”や、”A Pattern Language”という著書が有名で、住み心地のよい街や建物に共通して見られる、昔から繰り返し現れるパターンについて書いている。例えば、小高い場所、小さな公園、路上のプライベートテラスなど、A Pattern Languageでは、250あまりのパターンを挙げて解説している。居心地のよい場所・快適な生活を作り出すには、こうした先人の見出した、よいパターンを取り入れることが、間違いなく効果がある方法である。
前回、「なりよく生きる」を書いたのは、もう2年半も前のことだが、最近、この、パターンランゲージについて再考する機会があったときに、アレグザンダーさんも、街や建物の「なりよい」ありかたを考えた人だったのだろうと思った。前回のおさらいをすると、三河弁の「なりよい」とは、無理なく、自然のありかたに沿って、という意味で使う。「なりよい」という言葉で、アレグザンダーさんの、Timeless Wayを説明するとしたら、こうなる。先人が、よいものとして見出し、繰り返し使ってきた「なりよい」パターン、それを、設計に取り入れて使うこと。古い三河人なら、これでTimeless Wayを理解できると思う。
その、Timeless Way of Buildingから、第1章の最初のフレーズを紹介しよう。
“THE TIMELESS WAY
It is a process which brings order out of nothing but ourselves; it cannot be attained, but it will happen of its own accord, if we will only let it.”
自分なりに日本語にしてみると、だいたいこんな意味になる。
「時を超えた道は、我々自身の中から秩序を引き出すプロセスである。それは、達成されるものではなく、単にその道に身を任せれば、自然と立ち現れてくるであろう。」
ちょっと、おおげさな気もするが、アレグザンダーさんは、Timeless Wayとは、強制的に達成するようなものではなく、自分たち自身の中にから自然に出てくる秩序だと言っている。Timeless Way、まさに「なりよい」。
最近パターン・ランゲージに触れたのは、会社で、GOF(Gang of Four)のデザイン・パターンを紹介する機会があったからである。GOFのデザイン・パターンとは、ソフトウェア業界では有名な本で、正式名称は「オブジェクト指向における再利用のためのデザイン・パターン」と言う。初版が1994年なので、もう30年近く前に、どうしたら「なりよい」ソフトウェアを作ることができるのか?という問題に、GOFのメンバーが、アレグザンダーさんの考えを応用して作ったのが、ここで紹介されている23パターンだった。変化の速いソフトの世界で、今なお設計の拠り所となって生きているこれらのパターン、その元はアレグザンダーさんの考える、「なりよい」ものの在り方だった。
日本では、慶応大学の井庭崇さんが、「学び」や「プレゼンテーション」を、それぞれ、ラーニング・パターンやプレゼンテーション・パターンとしてまとめている。こういった応用例を見ると、自分なりに、自分の生き方の、なりよいパターンをデザインしてみたくなる。
私の祖母からすると、アレグザンダーさんは息子ほどの年の人。何の関係もない2人だが、「なりよく」生きるという考え方を教えてくれた人として、自分の中では結びついている。
2017.9.30(土)
写真:The Timeless Way of Building 表紙(1979年)
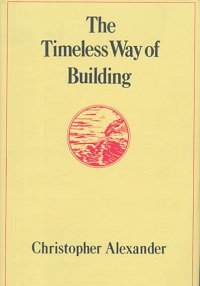
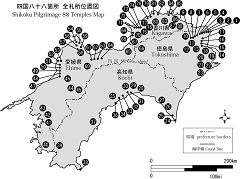

コメント