
方丈記の前半部分は、火事や地震などの災害が記録されている。それは、エッセーと言うよりも、どちらかと言えば当時の様子を記録した新聞記事のような趣がある。もちろん、長明自身の感想も書かれているし、新聞記事よりはかなり格調高い筆致で書かれているが、それでも、当時の災害の様子が、数値を使ったり、感情を交えない事実として表現されていて、単に作者の徒然なる想いを書いたものではない、記録文としての価値を感じる。方丈記の後半では、長明自身の生き方や想いが語られておりまさにエッセーなのだが、前半部分では、エッセイストと言うよりジャーナリスト長明と言ったほうがよさそうだ。
安元の大火の記述を見てみよう。以下、角川文庫の該当部分を参考にして、省略しつつ内容を紹介する。(・・・は省略部分)
「安元3年(1177年)4月28日、午後8時頃、都の東南の方角から出火して、西北へと燃え広がった。朱雀門、大極殿、大学寮、民部省などまで延焼して、一夜のうちに灰になった。・・・吹きちぎられた火炎が、100〜200メートルも越えて燃え移ってゆく。・・・この大火で公卿の屋敷16邸が全焼した。・・・総じて全都の3分の1を焼き尽くしたと聞いた。焼死者は男女合わせて数十人。・・・」
時刻、火元の位置や方角、どの建物がどの程度燃えたのか、被害者の数など、できるだけ事実を正確に書こうとしている文章である。なんせ850年も前のことなので、事実かどうかの確認は不可能だが、少なくとも災害の詳細を、事実をもって生々しく伝えており、当時の様子がとてもよくわかる。
同様に、養和の飢饉(1181〜82)の節でも、凄まじい京都の様子を、迫力の死者数で語っている。
「・・・(餓死者の)人数を把握しようとして、4月5月の2ヶ月に限って調査したところ、・・・一条から南、九条から北、京極から西、朱雀から東の路傍に放置された死体だけでも、全部で4万2千300余体もあった。・・・」
これは、仁和寺の隆暁法印という高僧が、死体の額に、成仏できるように梵字の「阿」を書いて回ったという話の後に出てくる、死者数のレポートである。何と、有効数字3桁の精度!2ヶ月に渡って、4万体の死体を数えたと言うが、単純に60日で割っても、1日に700体以上の死体を毎日数えたことになる。NHK古典講読の浅見先生は、長明ならそれぐらいのことやりかねない人だと言っていたが、本当だとしたら、ジャーナリスト魂を通り越して、ちょっと何かに取り憑かれた人のようにも感じる。
最後に、元暦の大地震での余震の記述を見てみよう。
「余震はしばらくの間続いた。余震と言っても、普通なら驚くほどの激しい揺れが、毎日2,30回ほど襲ったのだ。しかし、10日、20日と経つうちに、次第に間隔が遠くなっていった。ある日には1日に4,5回、それが2,3回になり、もしくは1日おき、2,3日おきに1回というふうに減っていった。おおよそ3ヶ月ほど余震が続いたように思う。」
余震が徐々に減っていく様子を、感覚でなく、1日何回、何日おきと言った数字で書き残しているので、800年以上前の余震の様子が誤解なく、正確に伝わってくる。
事実に基づく記述。これは、科学に通じる態度でもある。長明が現代に生きていたら、ジャーナリストになっていたかもしれないが、科学者になっていたかも知れないとも思う。寺田寅彦さんのような、科学者兼エッセイスト。政治が苦手だった長明さんのこと、そんな姿を想像するのもちょっと楽しい。
2019.6.22(土)
写真:安元の大火のだいたいの範囲。ググって、google mapに手描きした。

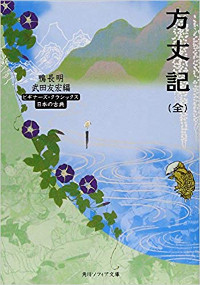
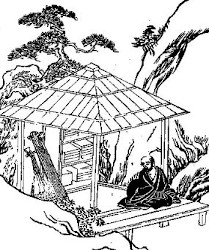
コメント