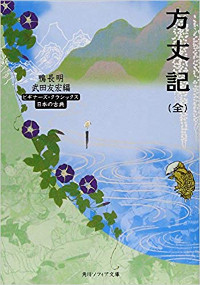
平安時代末期、火災・竜巻・飢饉・地震などの災害を立て続けに経験したうえに、家督を継げずに家を出て、最終的には京都郊外の里山に、DIYで小屋を建て、執筆活動にいそしんだ人がいた。そう、方丈記の著者として今でもファンが多い、鴨長明さんである。
先日、NHKラジオの古典講読で、長明さんの話を聞いたのがきっかけで、方丈記を読んでみた。正直に言うと、有名な冒頭の一節しか読んだことがなく、時代背景も、その無常観がどういうものかも、どんな人生を送った人なのかもほとんど知らなかったのだが、ラジオの浅見先生の解説と加賀美さんの朗読で、一時(いっとき)、長明と一緒に方丈記の世界を体験したような気がした。
方丈記の前半には、長明の体験した災害が生々しく描かれている。1177年の安元の大火では、当時の官庁街を含む京都の町の三分の一が、一夜にして消失した大火災の様子を書いている。大きな屋敷や行政府が一瞬で灰燼に帰した経験が、冒頭の一節を生み出す要因の一つとなったことは間違いない。行く河の流れは・・・に続く一節、「世の中にある、人と栖(すみか)と、またかくのごとし。」とは、まさに、一夜にして燃えて無くなってしまう、はかない建築物のことが念頭にあって書かれたものであろう。
大火に続く、治承の辻風(竜巻)、福原遷都(これは人災)、それに最後の元暦の大地震も、方丈記を読む限り大変な災厄だったに違いいないが、中でも養和の飢饉(1181,82 年)の記載が心に残った。水不足と台風などの水害で食料が極端に不足したことに加えて、衛生状態も悪化して疫病も広がって、京都だけで約四万人が亡くなったという。身なりの良い上流階級と思われる人が、なりふり構わず家を一軒一軒回って物乞いしているかと思うと、突然倒れて息絶えるといった記述や、馬や牛車が通れない程多数の餓死者の死体が道端に放置され、死臭が充満しているといった場面は、現代の日本ではとても想像できない凄惨なシーンを伝えている。今、世界中の外国人観光客が闊歩する京都の町に、1000年前、そんな光景が広がっていたことを、一体誰が想像できるだろうか。
当時の京都の町の人口が、十万人と言われているので、四万人と言えば半数近い人が餓死したことになる。しかも年を経ずして、大火災や遷都(半年もたたずに還都したが)、大地震を経験しても、なお都であり続けた京都という街。更に、「京都 地震」でググってみれば、長明が書き残した元暦の大地震の他にも、多くの大地震が繰り返しこの地を襲っていることがわかる。やられても、しぶとく立ち直って生き続けてゆく、そんな京都の街の力強さ、粘り強さを感じ、東北と京都が重なって見えた。方丈記は、そんなふうに読むのが本当の読み方なのではないかとも思った。
2019.6.17(月)
写真:方丈記 角川ソフィア文庫表紙
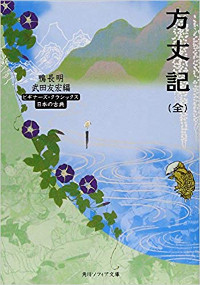
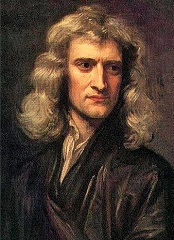

コメント