
NHKカルチャーラジオ・芸術その魅力で、伝統文化ジャーナリストの氷川まりこさんが、能楽鑑賞入門という題で話しているのを聴いた。その中で心に残った話題をいくつか取り上げてみたい。まずは能の構えから。
人間の身体の基本形は「立つ」ことである。足の裏を地面に付けて地面に立つ。このあたりまえなことが、能では全くあたりまえではない。能楽師が舞台に立つのは、構えと呼ばれ、それはこんな立ち方だと言うことだ。指は軽く握り、手の甲を前に向け、少し肘を両側に膨らませ、できる限り前傾したうえで胸を張り、あごを引き、おしりの穴をキュッと上に引き上げるように立つ。
初心者がやろうとしても、体中に余分な力が入ってしまい、不自然で、とても美しい立ち姿とは呼べないだろう。しかし、鍛錬によってこの構えを身に付けた能楽師が舞台に立つ姿は、ただ単に立っているよりも、はるかに舞台上で映える、美しい立ち姿となる。見ている側も背筋がピンと伸びるような清々しい構え、退屈な基本の訓練の後に得られる素晴らしい技と言ってよい。
太極拳にも基本の型がある。太極拳には「太極拳稽古要諦」という24の基本事項があるが、これは美しく動くためのコツ集と言ってよい。例えばこんなものがある。No.3「沈肩垂肘」肩に力を入れずに沈め、肘は自然に垂らす。No.12「源動腰脊」動きの源は腰と背骨。No.20「胯与膝平」後ろ足の腿と前足の膝を同じぐらいの高さにする。これらの基本事項を体で覚えて再現できるようになったとき、見ていても美しい動きができるようになる。(自分はまだまだできない)
動きの基本は、何も能や太極拳だけでもない。テニスとか、スポーツ全般にもあてはまるだろう。テニスなら、基本の打ち方というものがある。エアーKとか、強烈なトップスピンとかではい、ごくあたりまえの球を打つ打ち方。実際のゲームでは、とても追いつかないようなボールに飛びついたり、相手の予想と逆方向に打ったり、インパクトの直前までどっちに打つかわからないように隠したり、形通りではない高度な技が見られるが、どれも、基本の打ち方ができていなければこういった華麗な打ち方はできない。
基本の型を身につけないと、実戦では戦えない。これは、能でも太極拳でも同じではないか。基本の立ち姿ができなければ、観客の見ている舞台に立つことはできない。動きの基本ができてなければ、美しい拳の動きはできない。
あまり一般に広げすぎてもいけないかもしれないが、プログラムを書くのだって、コンピューターの基本的なしみを知らずに書いたプログラムはダメな気がする。コンピュータの仕組みはもしかしたら知らなくてもよいのかもしれないが、言語の基本は必要。データ構造とアルゴリズム、コンパイラとインタープリタ、変数とスコープ、制御構造、クラスとオブジェクトetc.。基本を身に付けた人が書くプログラムと初心者のプログラムはやっぱり全然違う。プログラムにも基本の型がある。良い型をカタログにまとめたのが、デザインパターンと呼ばれ、これを基本として身に付けたら、ダメなプログラムは書かなくなる。
基本の型を身に付けることは、何事によららず大事。能の構えは、型を極めるという意味でいろんな洞察を与えてくれる。
2021.10.31(日)
写真:能楽(ロイヤリティフリー画像から)

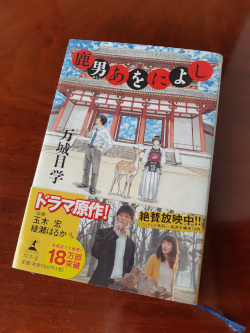

コメント