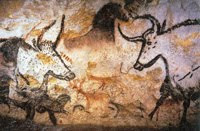 アイダ・ロルフの言葉を集めた、”Ida Rolf Talks About Rolfing and Physical Reality”というタイトルの本がある。「アイダ・ロルフ、ロルフィングと身体的リアリティを語る」と訳しておこう。しかし、これでは「リアリティ」の訳をサボっていて、生煮えの感が拭えないが、この”Reality”を「現実感」などと訳してしまうと、なんだかしっくりこない。カタカナのまま残しておいたほうがまだマシだと思う。
アイダ・ロルフの言葉を集めた、”Ida Rolf Talks About Rolfing and Physical Reality”というタイトルの本がある。「アイダ・ロルフ、ロルフィングと身体的リアリティを語る」と訳しておこう。しかし、これでは「リアリティ」の訳をサボっていて、生煮えの感が拭えないが、この”Reality”を「現実感」などと訳してしまうと、なんだかしっくりこない。カタカナのまま残しておいたほうがまだマシだと思う。
この本は、ロルフィングに関心のある方にはお薦めの本だが、題名の「リアリティ」が、ここ数年の間心に残っていた。そんな折、昔のメモを読み返していて、いくつか気付いたことがあり、「リアルとバーチャルの間」について書いてみようという気になった。と、言うのも、私はロルフィングを始める以前は、長年、ITと言うバーチャルな世界に身を置き、フィジカル・リアリティと無縁な生活を送ってきた後、バーチャルとリアルの間を渡ってきた人間だからなのだと思う。
ITの世界では、「バーチャル・リアリティ(VR)」という言葉が盛んに言われた時期があった。今から10年以上前のことになろうか。遠隔地からの入力情報を、自分のいる場所で再現し、あたかもそこに居るかのような感覚を作り出すこと、更に、自分のリアクションを遠隔地に伝えること、簡単に言うとそれがVRと言ってよいかと思う。今でこそ世間でそれほど騒がれなくなったのは、下火になったのではなくて、他の技術と同様に、普通に実用化されるようになったということである。遠隔医療や危険な場所での作業、あるいは、広い意味ではフライトシミュレーターなども、VRの技術として既に実用化されている。
バーチャル・リアリティでは、一旦数値化されたバーチャルな情報を、人間がリアルに感じられるように再現する、と言った意味合いがある。では一体、人間にとってリアルとな何だろうか?と思う。文学や芸術の世界でも、リアリズムと分類される分野があるように、この問いはヒトが絶えず問い続けて来たものに違いない。人類最古の絵画といわれるラスコー洞窟の壁画に描かれた牛や馬など姿の、なんとリアルなことか。動物たちのリアルな手触り、息、臭いなどを、そのまま壁に絵として再現したいと言う人間の本能のようなものを感じるのは、私だけではあるまい。
その意味では、絵画もバーチャル・リアリティの1つの形態である、と言ってもよいのではないかと思えてくる。描かれる対象はリアルなモノ、あるいはリアルな心象風景であるが、実際に描くのは、キャンバスと言う、言わば抽象的なモノである。VRの例では、キャンバスはコンピューターの中の数値と対応させてもよかろう。とは言っても、画家にとっては、キャンバスほどリアルなものはないであろうが。プログラマにとって計算機上のデータ以上にリアルなものがないのと同じであり、その辺は少し立ち入った考察が要りそうである。そう言えば、哲学にも、実存主義などと言う人たちもいたようだし。まぁ、これ以上は、今後の楽しみにとっておくこととしよう。
Dr.アイダの時代には、VRの技術はまだ誕生以前だっただろうし、アイダがラスコー洞窟の壁画を見たことがあるかどうかも不明だが、リアリティの原点が、壁に描かれた動物たちの絵にあると言っても、にっこり笑って「そうだね」と言ってくれそうな気がする。次回は、もう少しリアルな話題で、身体感覚と感情の関係について書いてみたいと思っている。
2010.9.26(日)
写真:ラスコー洞窟の壁画(Wikipediaより)
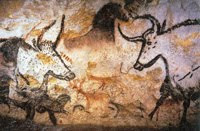
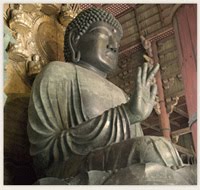
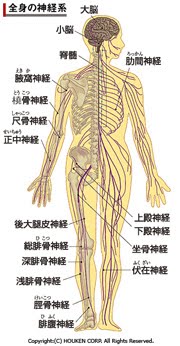
コメント