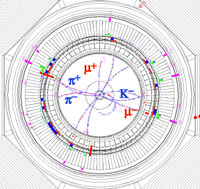 最近、ヒッグス粒子発見のニュースがあったばかりだが、その前後から、何となく物理関係の本がマイブームになっていて、何冊か乱読している。ベストセラーになった、大栗博司さんの「重力とは何か」(幻冬舎新書・2012年)とか、フランク・ウィルチェックの「物質のすべては光」(早川書房・2009年・これはまだ途中)とか、少し前の本だが、フランク・クロースの「自然界の非対称性-生命から宇宙まで」(紀伊國屋書店・2002年)など、興味の赴くまま読んでいる。(関係ないが、日本人の著者だと「さん」をつけたくなるのに、外国人だとさん付け表記に違和感があるのはなぜだろうか?)
最近、ヒッグス粒子発見のニュースがあったばかりだが、その前後から、何となく物理関係の本がマイブームになっていて、何冊か乱読している。ベストセラーになった、大栗博司さんの「重力とは何か」(幻冬舎新書・2012年)とか、フランク・ウィルチェックの「物質のすべては光」(早川書房・2009年・これはまだ途中)とか、少し前の本だが、フランク・クロースの「自然界の非対称性-生命から宇宙まで」(紀伊國屋書店・2002年)など、興味の赴くまま読んでいる。(関係ないが、日本人の著者だと「さん」をつけたくなるのに、外国人だとさん付け表記に違和感があるのはなぜだろうか?)
その中でも、立花隆さんの、「小林・益川理論の証明」(朝日新聞出版・2009年)は、いろいろ面白かった。これは、小林・益川両氏がノーベル賞を受賞(2008年)する直接的なきっかけとなった、素粒子実験に焦点をあた本である。おもしろかった理由はいくつかあるのだが、その1つは、この本が、雑誌の連載記事を本にまとめたものであるため、実験の進捗に伴う臨場感がすごく伝わってくる点である。朝日新聞社の科学雑誌「サイアス」に連載されたもので、筑波にある高エネルギー加速器研究機構(KEK)のBファクトリーでの実験の様子が、関係者のインタビューを元に、毎月リポートされている。連載が進むにつれて、粒子ビームのルミノシティ(粒子の個数)の値が上がっていったり、それによる機器の損傷に知恵を絞って対処したり、アメリカのライバル研究所の実験値にやきもきしたり、お盆休みが入ったりと、読みながら、一緒に実験しているような気分になって、とても楽しかった。
と言うのも、私も、遠い昔の学生時代に素粒子実験を専攻し、Bファクトリーの前身である、加速器に取り付けられた、トリスタンという検出器の製作に参加していたことがあるからである。それで、当時の雰囲気が脳裏によみがえってきて、とてもなつかしく感じた次第である。その当時(1985-86年頃)はまだトップ・クォークが見つかっておらず、KEKで発見すべく実験装置を作っていた。私は、実験が始まる前に修士過程を修了して就職してしまったので、実際の実験には立ち会ってないのだが、その後、トップ・クォークはトリスタンで検出できる質量より重かったため検出できず、結局、アメリカのフェルミ研究所の実験施設で発見された(1995年)。
この本がおもしろかった理由の2つ目は、連載が途中で唐突に終わっている点にある。これは、朝日新聞出版がサイアスの廃刊(2000年)を決めたため、連載を継続できなくなったのであるが、このあたりの経緯も、最終回に書かれており、それがまたなかなかおもしろい。不採算部門は切り捨てると言う会社の方針と、科学と日本社会を結ぶ重要なメディアであった「サイアス」(旧科学朝日)の存続を求める人々の声という咬み合わない話。私も、中学・高校の頃に科学朝日を時々買って読んでいた科学少年だった者として、この雑誌がなくなってしまうことは寂しいと思った記憶がある。しかし、反対者の署名を集めて朝日新聞の責任者に送れば廃刊は中止になるだろうと思った立花さんらの考えは、企業の生き残りの論理の前では甘かったようだ。きちんとした科学雑誌が採算のとれるような、科学が文化として根付いている社会は、日本にはまだ期待できないのだろうか。
2012.8.3(金)
写真:KEK Belle Event Gallery(http://belle.kek.jp/belle/events/)より
B中間子崩壊イベントの例
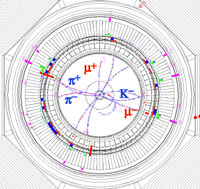


コメント