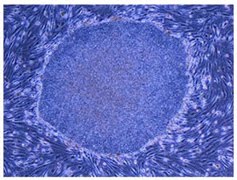 最近iPS細胞の研究成果がしばしば新聞紙上を賑わしている。そこで、iPS細胞についての解説書を2冊ほど読んでみたのだが、確かにすごい技術である。でも、いろいろと疑問が湧き上がってきた。まず、これは、科学なのだろうか、技術なのだろうか?
最近iPS細胞の研究成果がしばしば新聞紙上を賑わしている。そこで、iPS細胞についての解説書を2冊ほど読んでみたのだが、確かにすごい技術である。でも、いろいろと疑問が湧き上がってきた。まず、これは、科学なのだろうか、技術なのだろうか?
アルキメデスの時代から、科学と技術の間には明確な境界はなかったと思う。大きな船を進水させるために、テコの原理を考案したり、王冠が純金かどうかを確かめるためにアルキメデスの原理を思いつた話などから考えると、技術的な要求があって科学的な原理が発見されていた時代があったように思われる。その頃の科学と技術は、分かちがたく同居していたはずである。
時代が下ると、科学と技術は分離されてきた。科学は、世の中には役に立たない研究だけの世界になり、技術は真理の探究活動には関わらず、人間生活に役立つモノ作りを担うようになった。大学では、理学部と工学部はそもそも入学時点で別々だったりする。理学の研究者が下手にモノづくりなどやっていると、不真面目だと思われたり、工学の研究者が基礎研究などをやっているのは、研究費の無駄遣いだと思われたりする風潮は、今でもあるように思う。
しかしながら、科学と技術は、別れてはいても、互いに強く影響しあってきた。科学を進めるためには、最新の技術を使う必要があったし、技術を発展させるためには、新しい科学の知見を応用する必要があった。大口径の望遠鏡があって初めて星の観察ができ、星の観察なしには、学問としての天体物理学はありえない。また、天体観測が基礎となってニュートンは力学を整備したが、力学なしにはスペースシャトルの設計はできない。同様に、量子力学なしに集積回路はできなかったし、コンピュータなしにはゲノム解析など無理だったろう。世の中、相互作用で進んでいるのである。
最近は、学際的な活動も盛んになってきて、科学と技術の間は、また近づいてきているように感じる。言葉自体も、いつの頃からか「科学技術」と言うのは、「科学」+「技術」ではなく、1つの概念として使われている。
iPS細胞の研究は、科学技術の典型例だと思う。生命の素と言う、科学の最先端の領域でありながら、医学的な応用、中でも人体のあらゆる器官の再生医療への応用に直結する、医療技術領域の研究と言う面を非常に強く持っている。科学か技術かと言われれば、iPS細胞の研究は、明らかに「技術」研究的な側面が強いように思う。どうやったら万能細胞を「作り出せるか」と言う、モノ作りの研究であり、その意味では工学的な領域に近い。
この領域の研究は、生命を直接操作すると言う危険な側面があり、そのことだけで拒否反応を示す人々も多いようである。確かに、短絡的に手放しで進めてよい分野ではない。社会的なコンセンサスは大事である。そのことは十分認識したうえで、私は、この分野での「科学的」な知見の拡大にも期待はしている。所詮、「生命とは何か」と言う問いに答えたいとしたら、現状では、「これです」と一言でズバリと言えるような答えはなく、DNAであり、外界とのエネルギーのやりとりのある開放系であり、etc.etc.と言う多くの知見の集合体でしか答えの示せないものであることは事実である。そうだとしたら、その集合に、1つでも正しく、優れた知見を加えることは、この世界や自分たちが何者であるかを考える材料を豊かにすることであり、歓迎されるべきものではないだろうか。
問題は、この卓越した「技術」や「科学」的な知見が、悪しき方向に応用されないように見守る監視のありかたであろう。よく考えて、そして正しく実行してゆくような社会でありたいものである。
2009.8.20(木)
写真:科学技術振興機構(JST)のウェブサイト
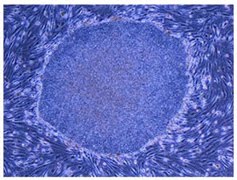
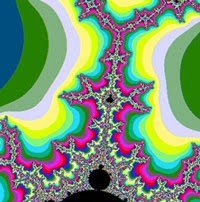

コメント