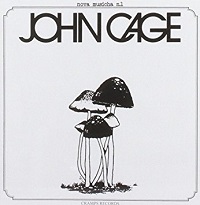
最近、新聞のコラムで、ジョン・ケージの4分33秒についての短文を読んだ。ジョン・ケージはアメリカの現代音楽家で、「4分33秒」とは、一定時間の無音状態を表現したこの曲(?)の通称である。この無音の楽曲のことは、以前何かで読んで知ってはいたが、久しぶりにその名前を聞いて、改めてその奇抜さと大胆さに感心した。
楽譜には、第1楽章・休み、第2楽章・休み、第3楽章・休みと書いてあるらしい。演奏者は、楽章の区切りを示すように指示されている他は、音を出さないでいる時間は自由で、楽器も、ピアノでもオーケストラでも何でもよい。曲名は、3楽章の合計時間とすることとされている。ピアニストのデイヴィッド・チューダーが初演で演奏しなかった時間が、3楽章あわせて4分33秒だったので、通称としてそう呼ばれるようになった。
ジョン・ケージによると、この曲のコンセプトは、無音を感じることではなく、演奏会場内外の様々な「音」を聴くことにある。例えば雨や風の音、鳥のさえずり、聴衆の足音など。これは、CDなどでも同様で、この無音の「曲」をCDプレーヤーにセットして、プレイボタンを押した後に聞こえる、様々な雑音に耳を傾けてみることが、本来の聴き方だと言うことだ。もともと彼は、「無音」を聴こうとして、研究所の「無響室」に入ってみたところ、自分の身体から発する血流の音や、聴覚神経そのものの作用による音を聴き、無音のないことを感じたことが、4分33秒につながった。
無音が無音でないように、真空もまた、何もない空間ではない。量子力学の教えるところでは、真空は、不確定性原理の許す時間の範囲内で、粒子と反粒子が生まれては消える、騒がしい世界であるようだ、4分33秒について考えているとき、数年前に読んだ「真空のからくり」(山田克哉著・ブルーバックス)という本を思い出した。量子力学では、物質は確率的にしか表現できない、ということは、数式で表されていて、頭では理解しているつもりでも、心から分かったと言えるような事柄ではないが、その事実の一つの側面が、この、真空の騒がしさだと言われると、なんだかちょっと「分かった」に近づけた気がする。
高名なホーキング博士は、ブラックホールにも温度があって、それに応じた熱放射があるはずだと予言した。通常の物質であれば、それを構成する分子や原子が振動する度合いに応じて、電磁波が放射されることは説明できるが、ブラックホールではその説明は難しい。しかし、ブラックホールの表面付近で対生成(ついせいせい)された粒子ペアーが、対消滅(ついしょうめつ)する前に、一つがブラックホールに落ち、一つが逃れ出てくる場合があるとすると、その質量分が放射されるとイメージすれば、ブラックホールからの放射を分かったように感じる。
この、騒がしい真空を、真空の「ゆらぎ」と呼ぶことがある。この世は静かな場所ではなく、ざわざわとゆらいでる。そのことを、不確定原理も、4分33秒も教えてくれている。騒がしいこの世界、静かで動きのない世界ではなく、真空から、わけの分からない物質や反物質が生まれては消える、ゆらめく世界。あーよかった、と思う。
写真:ジョン・ケージのCD
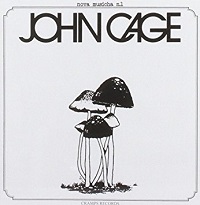
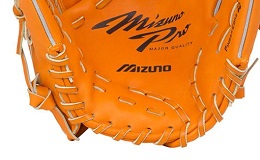
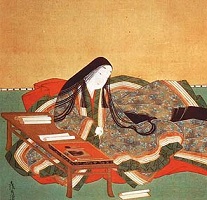
コメント
[…] 曲には、その曲を特定する名前がついている。名前のない曲はまずない。クラッシックの曲でも、ピアノ協奏曲第3番の第1楽章とかの名前がついていて、曲名を言うことで、ある音の連なりを特定できる。以前、科学考で取り上げたジョン・ケージの無音の楽曲でさえも、4分33秒という曲名(?)がついている。もし曲名がなかったら、曲を口ずさんで伝えるしかないが、それで「この曲」と特定することは難しい。 […]