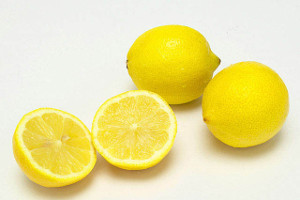
これまで、1kgとは、パリ郊外の国際度量衡局に保管されている金属の塊「国際キログラム原器」の重さ、と定義されていた。しかし、この科学技術の発達した時代に、いかに厳重に保管されているとは言え、未だに金属の塊の重さを基準としているのはいかがなものか、と言うことで、最近、1kgをこんな定義に変えるということだ。(2019.5.20より施行)
「キログラムはプランク定数の値を正確に6.62607015×10-34ジュール・秒(Js)と定めることによって設定される」(Wikipedia”キログラム”より抜粋)
これは、ちょっと定義になってなくて、本来はキログラムがプランク定数から、どのように設定されるかを定義しないといけない。プランク定数は、1Hzの光子のエネルギーを表すもので、科学では最も基本的な量の1つである。相対性理論によると、エネルギーは質量と等価(E=mc2)なので、ある質量を1とする、と決めるということは、それと等価なエネルギーを定義すればよいことになる。1kgと等価なエネルギーは、プランク定数と並んでもう1つの自然の基本的な定数である、光の速度(の2乗)を、このプランク定数で割ったエネルギーのことなので、プランク定数を決めると、質量を定義したことになる。つまり、重さは、プランク定数と光速度という2つの基本的な数によって定められるものとなった。
私は、この定義変更のニュースに接した時、昔、科学を学んだ頃のことを思い出して、量子の単位や光速度といった自然の基本的な性質の現れを、度量衡の根拠にしておくことは、とても好ましいことだと思ったし、同時に、遅すぎだよとも思った。アインシュタインが特殊相対性理論を発表して、光の速度は不変で、質量とエネルギーは等価だと言ったのも、光には粒子性があり、そのエネルギーは周波数にプランク定数を掛けたものだと言ったのも、同じ1905年で、もう100年以上も前のことだ。単位の世界が、やっと当時のアインシュタインの考えたことに追いついたと言うことか。
少し前になるが(2018.11月頃)、ある新聞のコラムで、この定義変更の話題が、こんなふうに書かれていた。重さとは、梶井基次郎の小説「檸檬」で表現されたような、それを持った時に感じる、確かな身体感覚を伴ったものであるべきで、新しい重さの定義は、その感覚からかけ離れてた、よそよそしいものになってしまった、と。まぁ、言いたいことは分かるし、身体感覚は大切ではあるが、この記事を読んだ時、もうちょっと自然や科学について考えようよ、と思った。レモンを手にした時に感じる瑞々しい重さの感覚、それは、量子の最小単位や不確定性の感覚、観測者の速度によって伸縮する時空の感覚の上に実感すべきものだと思う。それが自然の真の姿だし、私達人類も、その自然を構成する一部に過ぎないのだ。それは、決してよそよそしいものではなく、科学とは、確かな自然の感覚と理解すべきである。少し大げさに言うならば、そろそろ、人類は、科学をベースとした、新しい身体感覚を身に着ける段階に来ているのではないか、と思う。
lemmonと言えば、最近は、米津さんの曲でしょう。僕も大好きで、カラオケに行くとたいてい歌う。その歌詞に、「切り分けた果実の片方のように、今でもあなたは私の光」がある。さしずめ、自然という果実を切り分けると、プランク定数や光速度という変えようのない自然の性質があって、それと不可分の片割れとして重さが定義できる、ということだろうか。レモンを食べるときには、量子や時空の不思議に思いを馳せて、大いなる自然を感じてみてるのもよいのではないだろうか。
2019.2.10(日)
写真:フリー素材集 具満タンより

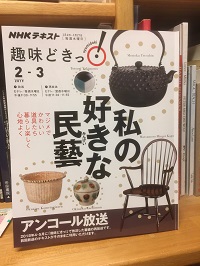

コメント