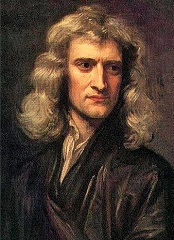
ニュートン力学は正しいが、その適用範囲は、対象物が光の速さより十分に遅い場合に限る。エンジェルスの大谷選手は時速160kmのスピードボールを投げるが、光の速度に比べれば1000万分の1程度なので、世界的な豪速球と言えども、ニュートン力学で十分に調べることができる。
アインシュタインは、相対性理論で光の速さまで扱える力学を作った。物理法則はどんな系でも変わらないという相対性原理と、光の速さはどんな系から見ても変わらないという光速度不変の原理の2つの基本的な前提から、「時間」や「長さ」が系(=観測者)の相対的な速度によって違って見えることや、質量とエネルギーが等価であることなど、現代科学の基礎となる重要な真理を導いた。人間の日常的な感覚では、長さも時間も、どこで誰が測ろうが同じ1秒は1秒なのだが、自然の真実は人間の感覚とは違っていて、系(=観測者)によってそれぞれ固有の時間や長さがあると言っている。
量子力学では、電子や陽子などのとても小さいものは、素粒子という言葉から想起されるような粒(つぶ)ではなくて、ぼやっと広がっていて、そこにある確率がこのぐらい、としか言えないような、確率的な存在だと言っている。しかし、それを射出してスクリーンに映すといった「観測」をすることで、確かにそこにある(あった)ことが確定する。それは、粒がどこにあるかの確率ではなくて、本質的に広がりを持った波としての存在が、観測した瞬間に粒になるという、日常的な感覚では理解できないものが、自然の真実だと言っている。そして、確率的な量子をこの世界の私達に見えるようにするのが、「観測する」という主体的な行為なのである。
ベイズ統計は、観測された事実をもとに、ある事象の確からしさを更新してゆくという、帰納的な確率の考え方である(正確な説明ではないが概ね)。それは、統計学と言う自然科学の一部ではあるが、その事象が世の中とリアルタイムに関わって変化してゆく、ダイナミックなありかたを扱う数学のように思う。世界と主体的に関わった結果、小さな事実が積み上がることで確からしさの精度があがってゆく世界。静かで変化のない世界ではなくて、騒がしく生きているこの世界を記述するのにはより適した考え方だと思う。
以上、相対性理論、量子力学、ベイズ統計と、現代科学の基本的な枠組みのいずれも、観測する主体にこそ真実があると言っている。何か、自分と世界の外側に神のような絶対的なものがあるのではなく、観測する主体があって、時間も空間も物質も初めて意味を持つ。物理的な事実なので、人間の存在には関わりなくそれが真実なのは分かっている上で、でも、これらの事実は、私たちの生き方に、「主体的であれ」と言っているように思うのだ。拡大解釈は承知、しかし、自然科学の事実であろうと、孔子の言った言葉であろうと、ブッダの教えであろうと、よく生きるために有用であれば、あえて拡大解釈することも、また良いことだと思う。
2019.06.01(土)
写真:ニュートン Wikipediaより
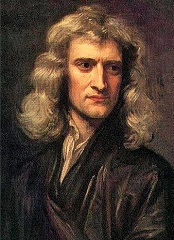

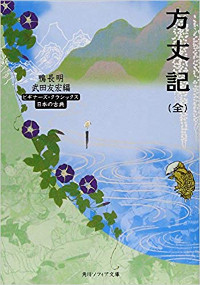
コメント